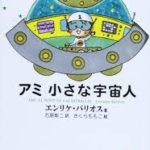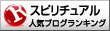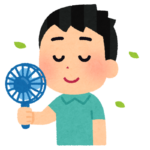「安全で、栄養価が高くて美味しい野菜」というと、
「オーガニック野菜」「無農薬野菜」ならオッケ~だと思う方は多いと思いますが実は違います。
長年、健康や良い野菜を作っている方々に
「良い野菜の選び方は何だと思いますか?」と、尋ねると、共通して同じ事を仰られます。
「オーガニックだから、無農薬だから良いとは限らない。
なるべく小さくて色が薄い野菜を選ぶと良いよ。」
まさにこの本はその内容をギューッと濃い解説をしてくれた素晴らしい一冊です♪
※楽天koboから試し読みが出来ます。
野菜は小さい方を選びなさい【電子書籍】[ 岡本よりたか ]
こんな濃い内容が1000円以下ってすごい安い!
お買い得の一冊だと心から思います。
解説の写真も、すごく解りやすいです。
在来種の種の多いトマトと、種が無いF1種のミニトマト。
農薬をかけすぎて左右対称に葉脈が伸びていない農薬をかけすぎた葉野菜。
本来、細長いはずの玉ねぎや、薄いはずのピーマン。
良い野菜選びのすっごい良い参考になります!
また、野菜はうっかり買いすぎて置いておいたら
どろどろになって腐ってしまった・・・という事あると思いますが、
それも実は自然なことではないのです!

そこらに生えてる自然の草花をもぎ取って持ってきて置いておくと、
腐ったりしないですよね?
「枯れる」。
本来は野菜も「枯れる」んです!
上記の書籍には、まるでほおずきのように乾燥したトマトや
和紙のようになったキャベツ、乾燥したごぼうのようになった大根の写真が載っていて、おお~なるほど!と、見とれてしまいました。
また、農薬や肥料を止めて虫食いが激減した小松菜やキャベツ。
何もせず放置しているのに伸び放題のキャベツ畑。
無肥料無農薬で、米ぬかやイネ科の枯れ野菜や腐葉土などを入れるコツなども書かれていて、
ほほ~なるほど!と、家庭菜園の参考になることがてんこもり。
そもそも
第4章には「本物の野菜は雑草と虫が育てる」とあります。
自然にあるものは自然とともに発生したものは
全て理由があるんだなぁと感動・・・
ちなみにうちにも小さな家庭菜園がありますが
毎年小さな小粒の野菜が沢山採れます。
こういったお話を聞くまでは、
「プロが作ったのではないからこんなものよね」なんて思ってたのですが
それどころか、自然が凝縮されたものであると知って感激。
これからも自然の恵みに心から感謝していただこう!と
心から想ったのでした♪
お店で買うときも、小さくて色が薄い訳ありみたいなのを
選ぶようにしています❤
野菜は小さい方を選びなさい (Forest 2545 shinsyo) [ 岡本よりたか ]
![野菜は小さい方を選びなさい (Forest 2545 shinsyo) [ 岡本よりたか ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9657/9784894519657.jpg?_ex=128x128) 990円(税込)【送料込】
990円(税込)【送料込】
Forest 2545 shinsyo 岡本よりたか フォレスト出版ヤサイ ワ チイサイ ホウ オ エラビナサイ オカモト,ヨリタカ 発行年月:2016年04月 ページ数:215p サイズ:新書 ISBN:9784894519657 岡本よりたか(オカモトヨリタカ) 環境活動家、(社)自然栽培ネットワークTokyo代表理事、空水ビオファーム八ヶ岳代表、命のリレーの会代表。昭和33年福井県生まれ。CMクリエイター、TVディレクター等の取材を通して、農薬、除草剤、肥料が環境にもたらす破壊的ダメージを知り、40歳半ばで山梨県北杜市の八ヶ岳南麓にて、無農薬、無肥料、無除草剤、自家採種である自然栽培と自然農法で小麦や野菜の栽培を始める。農家への無肥料栽培の普及・啓蒙を行う傍ら、無肥料栽培を可能にする自然の循環について紹介する無肥料栽培セミナーや、自宅で行うプランター無肥料栽培ワークショップや種取りワークショップ、上映会を定期的に行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 第1章 肥料や農薬がなくても野菜は育つ/第2章 有機野菜だから安全…ではない/第3章 不自然な種が不健康な食べものを生む/第4章 本物の野菜は雑草と虫が育てる/第5章 本物の野菜の選び方/第6章 本物の野菜はカンタンに作れる 野菜は大きい方が美味しそうに見え、お得感もあります。しかし野菜には「本来の大きさ」があり、その大きさには意味があるのですー2万人を超えるフォロワーの共感を呼ぶ著者が明かす、誰も知らなかった野菜の常識。 本 ビジネス・経済・就職 産業 農業・畜産業 新書 美容・暮らし・健康・料理 新書 その他
野菜は小さい方を選びなさい【電子書籍】[ 岡本よりたか ]
![野菜は小さい方を選びなさい【電子書籍】[ 岡本よりたか ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9756/2000004539756.jpg?_ex=128x128) 990円(税込)【送料込】
990円(税込)【送料込】
<p>■2万人のフォロワーの共感を呼ぶ著者が明かす、<br /> 誰も知らなかった野菜の常識とはーー</p> <p>あなたは、次の理由で野菜を選んでいませんか?<br /> だとしたら、あなたの野菜選びは間違っています。</p> <p>・JASマークが付いている<br /> ・有機栽培と表示がある<br /> ・無農薬だったら安心<br /> ・有機野菜だから安全<br /> ・オーガニックは栄養がある<br /> ・大きい野菜の方がお得<br /> ・色の濃い野菜は栄養価が高い<br /> ・みずみずしさは新鮮さの証<br /> ・甘味がつよいのは美味しい証拠<br /> ・形や大きさが揃っているもの</p> <p>オーガニックや無農薬、有機栽培の野菜だったら、<br /> 「安全で信頼できて美味しい」と思っていませんか?</p> <p>「化学肥料じゃなくて有機肥料だったら安全」<br /> そんなふうに思っていませんか?</p> <p>そんなことはまったくありません。</p> <p>オーガニックや有機栽培の表示の基準は<br /> 実に曖昧であり、農薬や化学肥料を使った野菜でも、<br /> オーガニックと表記する場合があります。</p> <p>有機栽培やオーガニックは、<br /> イコール無農薬と思い込んでいる人も多いと思いますが、<br /> それはかんちがいなのです。</p> <p>また、「化学肥料ではなく有機肥料であれば安全」<br /> というのも間違っています。</p> <p>どう作られた有機肥料なのかが、ポイントになります。</p> <p>そのことを知っている消費者はまずいません。</p> <p>そもそも、手つかずの自然のなかで、<br /> 植物は、肥料を与えられながら育っているでしょうか?</p> <p>「自然のなかでも動物たちの糞や死骸が植物の生長を助けている」<br /> と考えることはできます。</p> <p>では、田畑に撒かれる動物由来の有機肥料の量は、<br /> 自然のそれと比べて、適切でしょうか?</p> <p>人間の手が入れば入るだけ、<br /> 土のミネラルバランスは壊れていきます。</p> <p>バランスが壊れるから、<br /> 農薬が必要になり、肥料が必要になります。</p> <p>「無農薬無肥料」で作られた野菜を食べる。</p> <p>それが、最も健康で安全な選択です。</p> <p>■「スーパーで安全な野菜を見分ける方法」<br /> 「信頼できる野菜の入手方法」がわかる!</p> <p>無肥料無農薬の野菜は、<br /> 自然栽培や自然農とも言われ、<br /> そのよさが徐々に広まっていますが、<br /> まだまだ手に入りにくいものです。</p> <p>生産者と直接つながって、<br /> 購入することがベストですが、<br /> スーパーなどで買わざるを得ないことも多々あるでしょう。</p> <p>そこで、本書では、消費者のみなさんが、<br /> スーパーなどで簡単にチェックできる、<br /> 安全な野菜の見分け方をまとめています。</p> <p>ぜひ、あなたの暮らしに取り入れて、<br /> 美味しく健康な食事を楽しんでください。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。
野菜は小さい方を選びなさい フォレスト2545新書 / 岡本よりたか 【新書】
野菜は小さい方を選びなさい[本/雑誌] (フォレスト2545新書 117) / 岡本よりたか/著
![野菜は小さい方を選びなさい[本/雑誌] (フォレスト2545新書 117) / 岡本よりたか/著](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_1403/neobk-1942350.jpg?_ex=128x128) 990円(税込)【送料別】
990円(税込)【送料別】
ご注文前に必ずご確認ください<商品説明>野菜は大きい方が美味しそうに見え、お得感もあります。しかし野菜には「本来の大きさ」があり、その大きさには意味があるのです—2万人を超えるフォロワーの共感を呼ぶ著者が明かす、誰も知らなかった野菜の常識。<収録内容>第1章 肥料や農薬がなくても野菜は育つ第2章 有機野菜だから安全...ではない第3章 不自然な種が不健康な食べものを生む第4章 本物の野菜は雑草と虫が育てる第5章 本物の野菜の選び方第6章 本物の野菜はカンタンに作れる<商品詳細>商品番号:NEOBK-1942350Okamoto Yorita Ka / Cho / Yasai Ha Chisai Kata Wo Erabinasai (Forest 2545-Shinsyo 117)メディア:本/雑誌重量:200g発売日:2016/04JAN:9784894519657野菜は小さい方を選びなさい[本/雑誌] (フォレスト2545新書 117) / 岡本よりたか/著2016/04発売
【中古】野菜は小さい方を選びなさい / 岡本よりたか (新書)
 480円(税込)【送料別】
480円(税込)【送料別】
野菜は小さい方を選びなさい 新書 の詳細 無農薬だから安心、有機野菜だから安全、色の濃い野菜は栄養価が高い、そんな理由で野菜を選ぶのは間違っている。無肥料栽培の普及・啓蒙を行う著者が、不健康な食べものを生む理由や本物の野菜の選び方を解説する。 カテゴリ: 中古本 ジャンル: 料理・趣味・児童 園芸 出版社: フォレスト出版 レーベル: Forest 2545 Shinsyo 作者: 岡本よりたか カナ: ヤサイワチイサイホウオエラビナサイ / オカモトヨリタカ サイズ: 新書 ISBN: 4894519657 発売日: 2016/04/01 関連商品リンク : 岡本よりたか フォレスト出版 Forest 2545 Shinsyo
【中古】野菜は小さい方を選びなさい /フォレスト出版/岡本よりたか(新書)
【中古】野菜は小さい方を選びなさい / 岡本よりたか (新書)
野菜は小さい方を選びなさい/岡本よりたか【1000円以上送料無料】
 990円(税込)【送料別】
990円(税込)【送料別】
※商品画像はイメージや仮デザインが含まれている場合があります。帯の有無など実際と異なる場合があります。著者岡本よりたか(著)出版社フォレスト出版発売日2016年04月ISBN9784894519657ページ数215Pキーワードやさいわちいさいほうおえらびなさいふおれすと ヤサイワチイサイホウオエラビナサイフオレスト おかもと よりたか オカモト ヨリタカ9784894519657内容紹介野菜は大きい方が美味しそうに見え、お得感もあります。しかし野菜には「本来の大きさ」があり、その大きさには意味があるのです—2万人を超えるフォロワーの共感を呼ぶ著者が明かす、誰も知らなかった野菜の常識。※本データはこの商品が発売された時点の情報です。目次第1章 肥料や農薬がなくても野菜は育つ/第2章 有機野菜だから安全…ではない/第3章 不自然な種が不健康な食べものを生む/第4章 本物の野菜は雑草と虫が育てる/第5章 本物の野菜の選び方/第6章 本物の野菜はカンタンに作れる
野菜は小さい方を選びなさい/岡本よりたか【3000円以上送料無料】
 990円(税込)【送料別】
990円(税込)【送料別】
※商品画像はイメージや仮デザインが含まれている場合があります。帯の有無など実際と異なる場合があります。著者岡本よりたか(著)出版社フォレスト出版発売日2016年04月ISBN9784894519657ページ数215Pキーワードやさいわちいさいほうおえらびなさいふおれすと ヤサイワチイサイホウオエラビナサイフオレスト おかもと よりたか オカモト ヨリタカ9784894519657内容紹介野菜は大きい方が美味しそうに見え、お得感もあります。しかし野菜には「本来の大きさ」があり、その大きさには意味があるのです—2万人を超えるフォロワーの共感を呼ぶ著者が明かす、誰も知らなかった野菜の常識。※本データはこの商品が発売された時点の情報です。目次第1章 肥料や農薬がなくても野菜は育つ/第2章 有機野菜だから安全…ではない/第3章 不自然な種が不健康な食べものを生む/第4章 本物の野菜は雑草と虫が育てる/第5章 本物の野菜の選び方/第6章 本物の野菜はカンタンに作れる